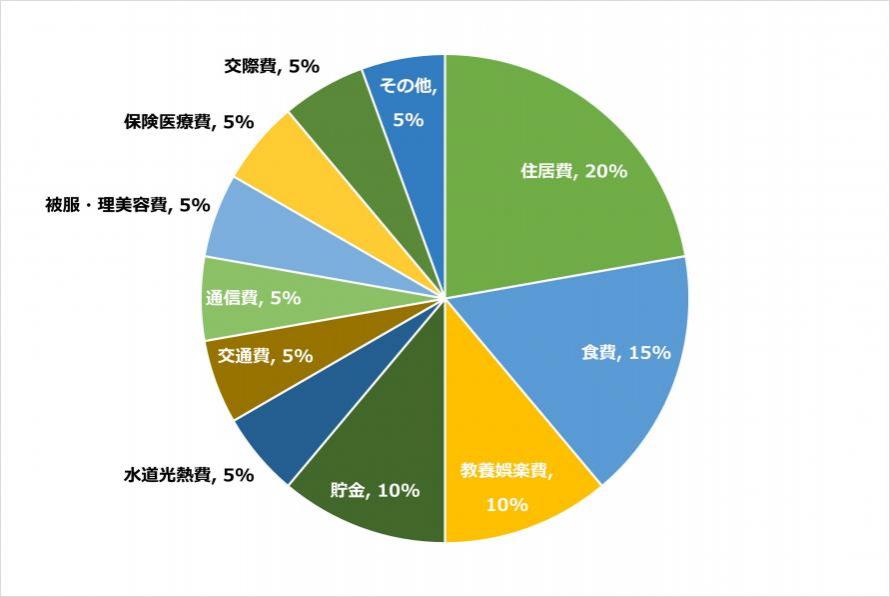石巻専修大学
経営学部 教授
庄子 真岐さん
仙台市出身。東北大学農学部卒業後、大手化学企業に就職し、4年間勤務する。2005年、東北大学大学院経済学研究科に入学し、2012年博士課程修了。石巻専修大学には2010年4月から勤務し、観光学に関する講義やゼミを受け持つ。2011年に第一子、2017年に第二子を出産し、仕事と育児を両立している。
社会人を経て教育者・研究者の道へ。観光によるまちづくりを実践

現在の会社(団体)を選んだ理由を教えてください。
もともとまちづくりや地域づくりに興味があったものの、漠然としていました。理系科目の方が得意だったため、農学部に進学しましたが、講義の中では、社会科学系の分野に興味関心を持ちました。早く社会に出たいという思いからまちづくりや地域づくりに関われる企業への就職活動を始めました。しかし、就職活動では希望のディベロッパーに内定をもらえず、大手化学企業に就職しました。仕事は医薬品の販売促進で、全国各地に出張があったのですが、いろいろな地域に触れる中で、「やはりまちづくりに携わりたい」という気持ちを捨てきれない自分に気づき、退職して大学院で学ぶことを選択。修士課程で学ぶうちに、実務に携わるよりも研究者や教育者の方が向いているのではないかと考えるようになり、博士課程に進んで地域計画等についてさらに研究を続けました。博士課程に在学中、石巻専修大学が教員を募集していると知り、応募して採用され今に至ります。
現在の業務内容を教えてください。また、仕事をする上で心がけていることはありますか?
石巻専修大学で観光学と地域経営論をメインに教えるほか、非常勤で宮城大学や宮城学院女子大学でも授業を受け持っており、合計すると週に8~9コマほど担当しています。自身の専門分野は地域計画や観光によるまちづくり。特に震災後の被災地をはじめ、イメージ的に不利な地域の観光をテーマに研究を行っています。心がけていることは、実践教育を取り入れること。私一人で教えられる領域には限りがあるので、大学の外に出て、まちづくりに携わる地域の人たちにも指導していただきながら、実社会で学ぶ体験型の教育プログラムを実践しています。

仕事と子育てを両立する上で、大切にしていることを教えてください。
両立させようと思わないこと、完璧を求めすぎないことです。仕事の時は仕事、子どもと過ごす時間は子どもと過ごす時間と割り切り、オンとオフの区別をつけるようにしています。幸い子どもたちも成長してきて、仕事が忙しい時にはきちんと説明すれば協力してくれるので、だいぶ楽になりました。
これから活用したい、または活用している・活用したことのある福利厚生や社内制度を教えてください。
産休・育休制度を取得したほか、現在進行形でお世話になっているのが、大学教員の「専門業務型裁量労働制」という制度です。業務の遂行手段及び時間配分の決定などを、教員の裁量に委ねることができるというもので、石巻専修大学(教員)でもこの制度を導入しています。時間が決まっている講義や学内業務以外は時間管理されないため、自分の裁量で仕事を進めることができます。時間の融通が利くというのは、育児をしている身からすると非常にありがたいですね。

あなたが思う宮城の魅力はなんですか?宮城で暮らす理由も教えてください。
最近、都会の利便性と田舎暮らしが両立している地域を指す「トカイナカ」という言葉を耳にするようになりましたが、宮城の魅力はまさに「トカイナカ」であることだと思います。仙台という大都市があり、その周りに個性的な市町村がたくさん存在しています。仙台に一極集中しすぎず、各市町村がもっとつながりを持てば、さらに魅力的な県になるのではないかなと思っています。宮城に住む理由は地元だからということに尽きますが、一度社会人を経験した際に宮城を離れたことで、地元に愛着を持っていることに気づくことができました。
今後思い描いているキャリアデザインは?そのために努力していることや、宮城県や企業に期待していることも教えてください。
鎮魂の祈りと石巻市の復興の様子を竹灯籠の光で映し出し、ゼミ生の楽しい企画で盛り上げる「竹こもれびナイト」という年1回のイベントを企画・運営して5年目になります。こうした地域の住民を巻き込んで一緒に楽しめる場をつくっていく活動は、今後も継続していきたいですね。教育面では、まちづくりを自ら企画し、実践していけるようなプレイヤーをたくさん輩出していきたいと思っています。県に期待するのは、まちづくりを志す学生がチャレンジしやすい環境の整備です。大学と観光協会やまちづくり会社などといった地域で活躍する事業者や個人をつなぐ体制づくりや、資金面の援助などを通し、いろいろなチャレンジが生まれやすい土台づくりをお願いしたいです。
学生インタビュー
社会人として得たスキルと研究者として得たスキルにはどのような違いがありますか?
企業で働いていた時の仕事は、今と大きくは変わりません。情報を集めてオリジナリティある視点で整理し伝える、という仕事は研究とほぼ同じです。ですが、研究者は精緻さや新規性を、企業はスピードが求められた印象はあります。研究を続けたいと思い大学教員の職に就きましたが、教員となり改めて気付かされたのは、大学の教員は研究者であると同時に教育者であるいうことでした。研究と教育は、似て非なるものなので、最初の頃はWワークのような感覚でした。試行錯誤しながら研究を続け、教育も自分なりに工夫してきました。研究の成果を教育に活かす、教育で得られた視点を研究に活かすことが求められていると感じています。
学生や進路に迷っている人へのメッセージをお願いします。
「こうあるべき」という前提を作りすぎないようにしましょう。完璧な会社、組織など存在しません。多かれ少なかれ不満を抱くと思います。不満に気を取られすぎると前に進めなくなります。だからこそ、自分自身が何をしたいのか、どうしたいのかを大切にしてください。この道が違うと思ったら、引き返せばいいのです。また、やりたいこと、目標や目的も常に見返しましょう。社会も変わります。だから社会における自分の目標や目的も変えていかないとズレが生じるからです。本を読むのも大事ですが、動いて得られたコトは、自分だけの財産になります。常に少しでいいから動き続けることが大事だと思います。「やってみよう。何とかなる。」という精神でまずは踏み出してみてください。


Interviewer
峯村 遥香さん 東北大学大学院
MY SCHEDULEある日の私のスケジュール
-
6:00
起床・朝食準備
起床後仕事を開始するまでの時間は、デジタルデトックスを心がけています。テレビはつけません。
-
6:30
ランニング、シャワー、身支度
体力づくりのため、3.5kmのランニングをしています。
-
7:20
子供たちを起こし、朝食をとります。子供たちを保育園へ送り出してから出勤します。
-
9:30
出勤
車通勤しています。この時間をドライブだと思い込んでいます。最近は、オーディオブックにはまっています。
-
9:40
講義
-
13:00
昼食
-
13:30
午後の業務
講義、ゼミ、学内会議、学外委員会、講義準備、研究の下調べ、学生対応などを行っています。
-
18:00
退勤
車の中で夕飯の献立を考えます。
-
19:10
保育園のお迎え
子供の顔を見ると疲れが吹き飛びます。一方、ここから就寝までの時間はほとんどノンストップです。
-
20:00
帰宅
夕食、片付け、洗濯、子供の宿題確認など。家事をゲームのように仕立て、子供たちにも手伝ってもらいます。
-
23:30
就寝
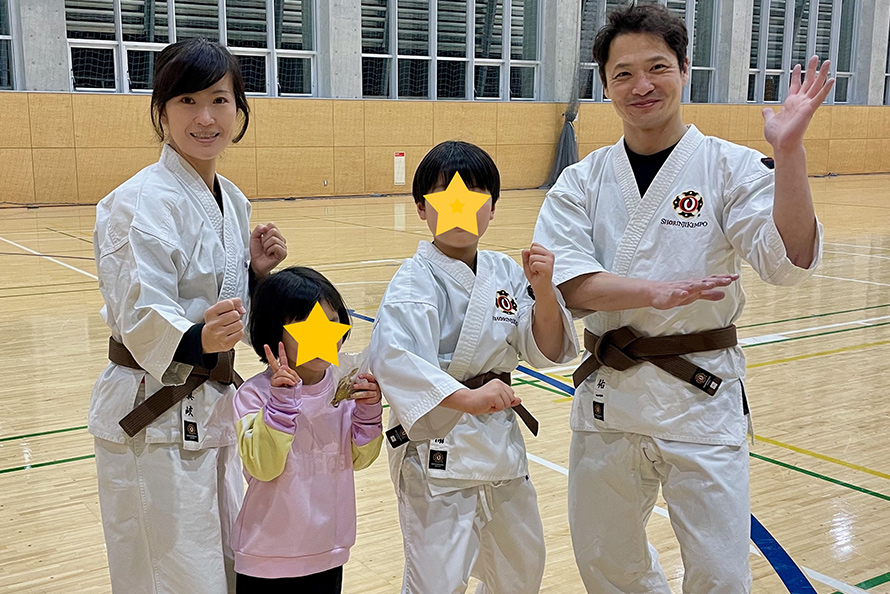
休日の過ごし方
土曜日は、研究会など仕事が入ることが多いですが、夕方からは、家族4人で少林寺拳法を習っています。昇段試験を受けたり、大会にも出たりするほど真剣に取り組んでいます。日曜日はなるべく予定を入れず、のんびり過ごすよう心がけています。
※記載内容は取材当時のものです。