ここから本文です。
田んぼの学校2025 広渕小学校
広渕ふるさと保全会広域協定は多面的機能支払交付金を活用して、石巻市広渕地区の農村環境保全活動に取り組んでおり、活動の一環として、広渕小学校と連携した啓発活動を展開しています。
目次
令和7年5月28日 田植え体験
5月28日、石巻市立広渕小学校5年生28名が、田植え体験に参加しました。
この体験は、広渕ふるさと保全会広域協定(多面的機能支払交付金活動組織)が主催し、児童たちが地域の農業や自然に親しむ機会として実施されています。
今年度は、宮城県の代表的な品種である「ひとめぼれ」を植えました。
はじめに、保全会の八木会長より開会のあいさつがあり、その後、学校ボランティアの桂谷氏より苗の植え方について説明を受けました。
事前に枠回しをしているため、線が交差する場所へ4から5本程度の苗を植えます。

(開会あいさつの様子)

(苗の植え方について説明を受ける児童)
説明を受けた後は、いよいよ田植え体験です。児童たちは赤組と白組に分かれそれぞれ苗を手に取り田んぼの中に入っていきました。
田んぼに入ると、児童から「冷たい」、「動きづらい」等といった声がありましたが、次第に田んぼの感触にも慣れ、一生懸命に苗を植えていきました。保全会の皆さんからアドバイスをもらいながら笑顔で協力し合う児童の姿がとても印象的でした。


(左:田植えをする赤組の児童,右:田植えをする白組の児童)
田植え後には、農事組合法人ひろぶち営農組合の本田氏に協力していただき、農業用ドローンの飛行を見学しました。普段は間近で見ることのできない大型ドローンの迫力に感動している様子でした。

(農業用ドローンを見学する様子)
活動終了後には、児童から感想発表があり、「昔の人は機械がない中で、田植えから稲刈りを人力で行っていたのがとてもすごいと思いました。」といった感想や「初めて田んぼの中に入り、手植えでの田植えをさせてもらえてとても貴重な経験となりました。」といった感想が聞かれました。

(感想発表の様子)
終わりに、保全会の高橋副会長から挨拶があり、今年の田植えは無事終了となりました。
広渕小学校では今年度も生き物調査や稲刈り体験を予定しており、1年を通して農業や自然について学ぶ貴重な時間が続きます。
令和7年8月5日 水稲生育調査・水質調査・生き物調査
8月5日、石巻市立広渕小学校5年生の児童21名が、水稲生育調査、水質・生き物調査を行いました。
はじめに、広渕ふるさと保全会広域協定の八木会長より挨拶をいただき、調査を開始しました。
水稲生育調査
5月に児童が手で植えた「ひとめぼれ」の生育状況を確認するため、代表の児童が稲の丈を測り、85センチメートルまで成長していることを確認しました。保全会の石垣副会長からは、「今年はひとめぼれを植えてもらったが、現在順調に成長している。」とお話をいただきました。

(稲の丈を測る児童)
水質調査
水質調査では、河南矢本土地改良区より水質調査キットの説明があり、水路の水のpHとCOD(化学的酸素要求量)を計測しました。児童たちは変化した水の色から結果を調べ、児童同士で結果を共有していました。結果はpHが6~7の中性、CODは6~8のやや汚れた水という結果になりました。


(水質調査の様子)
生き物調査
水質調査の後には、いよいよ生き物調査です。
児童たちは網をもって、2本の水路で生き物調査を行い、協力しながら生き物を採取してくれました。


(生き物調査の様子)
生き物調査の後には、採取された生き物の種類を判別を行いました。
「カラドジョウ」、「モツゴ」、「アメリカザリガニ」等の生き物が採取されたことを紹介し、アメリカザリガニ等の特定外来生物の取り扱いについても説明しました。



(左:カラドジョウ、中央:モツゴ、右:アメリカザリガニ)
調査が終わり、児童からは「水路にこんなに生き物が住んでいると思わなかった。」といった感想や「採取した魚はメダカだと思っていたが、違う種類の魚で驚いた」といった感想があり、田んぼが持つ役割について理解を深めていました。
その後、河南矢本土地改良区より記念品が贈呈され、保全会の雫石副会長より閉会の挨拶をいただき、今回の調査は無事終了となりました。

(記念品贈呈の様子)
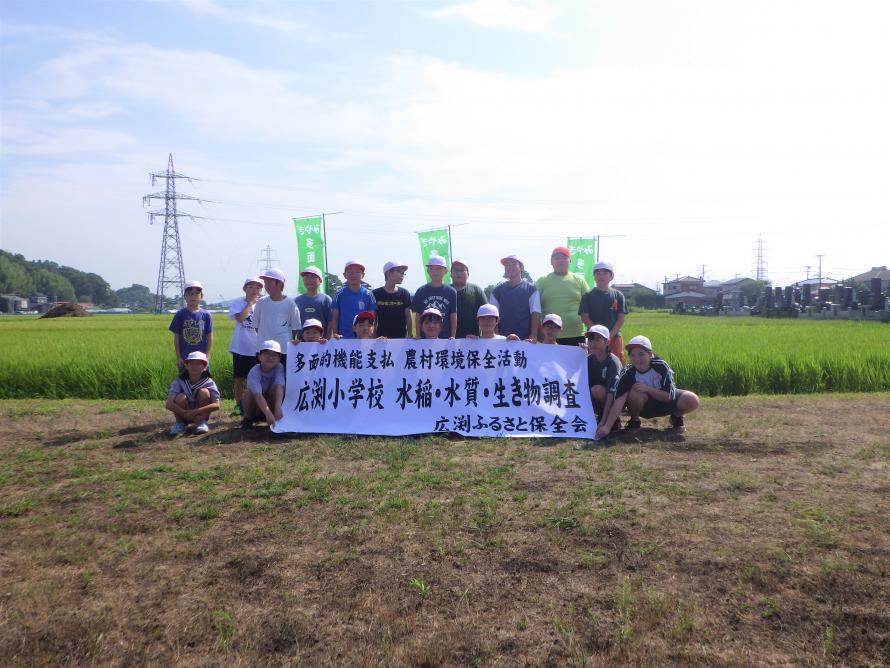
(集合写真)
令和7年9月26日 稲刈り体験
9月26日、石巻市立広渕小学校5年生26名が5月に植えた「ひとめぼれ」の稲刈り体験を行いました。
はじめ、農事組合法人ひろぶち営農組合の本田代表より手鎌を使った稲刈りの方法について、説明があり、児童たちは、鎌を手にして稲刈りを行っていきました。

(稲刈りの説明を受ける児童)
1株づつ刈った稲は、6株程度をひもで結び、稲の根本をそろえて一束にします。収穫後の稲は、水分を含んでいるため、日光や風で乾燥させることで米の品質を保つことができます。今年は「稲杭」へ稲束を積み上げる「棒掛け」までは行わず、刈った稲を稲束にするまでの過程を体験しました。


(左:稲刈りを行う児童、右:稲束を作る児童)
稲刈り体験の後には、児童たちから感想発表がありました。
「手鎌を使うのは初めてだったが、とても楽しかった。」
「保全会や地元協力の人たちからアドバイスをもらってうまく稲を刈ることができた。」
「手鎌での稲刈りを体験して、農家の大変さを実感した。」
といった多くの感想が児童から寄せられ、地元の農業への関心が高まっている様子でした。
石巻市立広渕小学校では5月の田植えから始まり、稲作や農業・農村をとりまく環境について理解を深めることができた1年間となりました。

(集合写真)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています